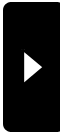昭和34年にあったこと
先月お誕生日を迎えたことをお伝えしたが、
私が生まれた昭和34年。
この年に何が起きたのか?
その前に
私の父親は外国航路の船員をしており、その関係で
海のそばの方が会いやすい ということで、母は長野県から
名古屋に居を移して住んでいた。
そこで私が生まれた。
昭和34年の1月に生まれ、その年の9月に伊勢湾台風が襲来した。
伊勢湾名づけられたように、名古屋は大被害を受けた。


母が住んでいたのは、名古屋市港区。
まさに海の近く。
そこの2階建てアパートに住んでいた。
ここからは母から聞いた話。
夜になり、雨風が激しくなり、窓ガラスは枠ごとはずれ吹き飛び、
雨は叩きつけるように部屋の中に吹き付けた。
2階建てアパートの2階に母と生後8ヶ月の私。
雨は夜半になっても止まず、激しさを増してゆく。
アパートの1階は天井まで浸水。
1階の住民も全て2階に避難してきた。
2階の入り口まで水が来たそうだ。
朝になり、ようやく雨は上がったが、水は引かず
見動きのとれない状態。
ミルクも与えられない状態で私は泣き叫んでいる。
そこへ、1艘の手漕ぎボートが来た。
母を心配した近くの牛乳屋さんのおじさんが様子を見に来てくれたのだ。
それも、牛乳を持って。
ようやく助かった母と私。
伊勢湾台風被害に遭い、その対策として建てられた県営住宅に移り住んだ。
それは小牧にあった。
そこで私は小学校上がる前まで過ごした。
こう聞くと、よくもまあ乳飲み子を抱えた母一人
伊勢湾台風の中、生き延びることができたもんだと思う。
しかし、今度は父親は昭和56年9月。
奄美大島沖にて乗務していた貨物船が台風に遭い、
甲板を巡回していた時に大波が船を襲い、
甲板に叩きつけられ、亡くなってしまった。
波乱万丈過ぎる一家だわ。
今は天下泰平。
いろいろな人の助けにより、60年生きてきました~。
三つ子の魂 百まで
私が「伊那保育園」出身ということはここでも何度か書いている。
先日の6組同級会でも伊那保育園出身者が何名かいた。
小川くんと中村くんだ。
その時の印象に残っているエピソードがある。
年長さんは2組に別れていた。
「川組」と「山組」
私は「川組」に所属していた。
山組の方には、保育園の息子だった中山くんや、中村くん、小川くん、湯田くん、
大庭くん、白石さん達がいた。
どちらかと言うと川組よりも山組の方が元気が良かった。
お昼寝が終わり、さあ帰りの時間という時に
教室から退出する際に山組の男子4名くらいが
一列渋滞になり、歩きながら
「オ~、スッザンッナ、泣くんじゃね~!!」
と歌いながら腕を振り上げ、行進してゆく姿を覚えている。
その中にいたのが中村くん(サポ)であった。
私はサポとはサポが新町、私が双葉町という非常に近い場所に
住んでいたので小学校時代もクラスは違ったが
よく見知っていた。
保育園時代の徒党を組んでのし歩いていたサポの印象が強く、
どうしても私の中のサポ像は
「近寄りがたい怖い人」 という感じだった。
中学時代は花形バスケ部だったので、よけいに近寄りがたさは
強まっていったと思う。
それがこの会で一気に距離が縮まった。
そして、私の「サポイメージ」は大きく旋回した。
なんとなく近寄りがたかったイメージだったのが
『なんて【人たらし】な奴なんだ!』
人たらしと言うと、女たらしと表現されるように
あまりいい意味には使われない。
人をだましたりという意味に使われているが、
私はこと「人たらし」という言い方をする時は
褒め言葉に使っている。
例えば、豊臣秀吉。
彼がその「人たらし」であったと言われている。
人心掌握するのがとってもうまい人
のことをそう称したりする。
私はサポがこの「人たらし」だ、と感じた。
まず、人の心を逸らさない話術・話題。
人を傷付けない心配り。
自分のことをさらけ出し、相手の心を開かせる。
そんなことがサラッとできる人 と思った。
オ~、スザンナがよくぞここまで・・・・・と感心した。
同窓会
今まで自分が思っていたイメージと全く違う別の顔が見れる
楽しさ・驚きがある。


まんまの顔してるね。
やんちゃで、いたずら好きで、きかん坊だったんだろう。
他の子達も変わらん!
この頃からもう55年も経っているのにね。
先日の6組同級会でも伊那保育園出身者が何名かいた。
小川くんと中村くんだ。
その時の印象に残っているエピソードがある。
年長さんは2組に別れていた。
「川組」と「山組」
私は「川組」に所属していた。
山組の方には、保育園の息子だった中山くんや、中村くん、小川くん、湯田くん、
大庭くん、白石さん達がいた。
どちらかと言うと川組よりも山組の方が元気が良かった。
お昼寝が終わり、さあ帰りの時間という時に
教室から退出する際に山組の男子4名くらいが
一列渋滞になり、歩きながら
「オ~、スッザンッナ、泣くんじゃね~!!」
と歌いながら腕を振り上げ、行進してゆく姿を覚えている。
その中にいたのが中村くん(サポ)であった。
私はサポとはサポが新町、私が双葉町という非常に近い場所に
住んでいたので小学校時代もクラスは違ったが
よく見知っていた。
保育園時代の徒党を組んでのし歩いていたサポの印象が強く、
どうしても私の中のサポ像は
「近寄りがたい怖い人」 という感じだった。
中学時代は花形バスケ部だったので、よけいに近寄りがたさは
強まっていったと思う。
それがこの会で一気に距離が縮まった。
そして、私の「サポイメージ」は大きく旋回した。
なんとなく近寄りがたかったイメージだったのが
『なんて【人たらし】な奴なんだ!』
人たらしと言うと、女たらしと表現されるように
あまりいい意味には使われない。
人をだましたりという意味に使われているが、
私はこと「人たらし」という言い方をする時は
褒め言葉に使っている。
例えば、豊臣秀吉。
彼がその「人たらし」であったと言われている。
人心掌握するのがとってもうまい人
のことをそう称したりする。
私はサポがこの「人たらし」だ、と感じた。
まず、人の心を逸らさない話術・話題。
人を傷付けない心配り。
自分のことをさらけ出し、相手の心を開かせる。
そんなことがサラッとできる人 と思った。
オ~、スザンナがよくぞここまで・・・・・と感心した。
同窓会
今まで自分が思っていたイメージと全く違う別の顔が見れる
楽しさ・驚きがある。


まんまの顔してるね。
やんちゃで、いたずら好きで、きかん坊だったんだろう。
他の子達も変わらん!
この頃からもう55年も経っているのにね。
君達が教えてくれた
長いお盆休みもおしまい。
皆さんはどう過ごされましたか?
私はダンナと飲んだくれていました。
会社勤めもしていないと、話し相手は自然 ダンナくらいしかになってしまう。
お店のお客さんとも話しはするが、
相当仲の良い人でないかぎりそんなに深い話はできない。
ふとこんなことを想い出した。
中学生の頃、社会のこと、世間のこと 何も知らなかった私に
いろいろなことを教えてくれたのは同級生達だった。
テレビから流れてくる歌謡曲くらいしか知らなかった時に
転校生の名古屋くんが教えてくれた「Chicago」という外国のバンド。
男子達はキャンバス地のカバンにこのロゴマークをマジックで
描いていた。

音楽話では、他には「ビートルズ」。
その頃、ちょうどベストアルバム2枚組みが発売され、
それを元は誰が購入したものだったか、
とにかく皆でこぞってそれを借りて聴いていた。

私に「かぐや姫」を教えてくれたのは、吉澤章司くんだった。
「かぐや姫 さーど」という神田川の入ったアルバムを買った。

ラジオの深夜放送が大好きで、そんな話をいつもしていたのが
北原雅典くん。
オールナイトニッポンが好きで、いっつもラジオの話ばかり聞かせてくれた。
その影響で私もラジカセを買った。
北杜夫を私に教えてくれたのは、
合唱クラブの先輩・建石徹さん。
とにかく、「船乗りクプクプの冒険」は面白いから読んでみて。
と、私にではなく、他のだれかに言っていたのを聞きかじり
私も買って読んでみたら メチャクチャ面白くて
それ以降、北杜夫にはまり、ドクトルマンボウシリーズも、さみしい王様も読破した。

この本は、逆に私が吉澤くんに「面白いから読んでみな。」と薦め、
やはり彼がおおいにうけ、はまっていった。
そして、私の以降の人生に大きく関わった
「石森章太郎・サイボーグ009」を教えてくれたのが
上島貞憲くんだった。

彼は文庫本全巻を持っており、数巻づつ貸してくれ、
読み終わるとまた次の巻を渡してくれるという。
全10巻。読み終えるのに時間はかからなかった。
これ以降、私は少年漫画にもはまっていったのだった。
と、中学時代、私の人格を形成するのに大いなる影響を与えたであろう
いろいろな事柄を教えてくれたのは全て同級生
それも男子達だった。
他にもハム(アマチュア無線)の試験を受けに一緒に勉強したり、
男子達は私の知らない世界の扉を開けてくれた。
女子から何も影響がなかったというわけではないが、
あまり琴線に触れるような刺激的なことはなかったように記憶している。
というか、あまり記憶がない・・・・・・。
なので女子高校に進んだ私に刺激を与えてくれる男子達が
周りからいなくなったことは、
私にとって非常に世間の様々なことを知る機会が喪失した
と言っても過言ではないような気がする。
中学時代、君達に教えてもらったんだよ。
皆さんはどう過ごされましたか?
私はダンナと飲んだくれていました。
会社勤めもしていないと、話し相手は自然 ダンナくらいしかになってしまう。
お店のお客さんとも話しはするが、
相当仲の良い人でないかぎりそんなに深い話はできない。
ふとこんなことを想い出した。
中学生の頃、社会のこと、世間のこと 何も知らなかった私に
いろいろなことを教えてくれたのは同級生達だった。
テレビから流れてくる歌謡曲くらいしか知らなかった時に
転校生の名古屋くんが教えてくれた「Chicago」という外国のバンド。
男子達はキャンバス地のカバンにこのロゴマークをマジックで
描いていた。

音楽話では、他には「ビートルズ」。
その頃、ちょうどベストアルバム2枚組みが発売され、
それを元は誰が購入したものだったか、
とにかく皆でこぞってそれを借りて聴いていた。

私に「かぐや姫」を教えてくれたのは、吉澤章司くんだった。
「かぐや姫 さーど」という神田川の入ったアルバムを買った。

ラジオの深夜放送が大好きで、そんな話をいつもしていたのが
北原雅典くん。
オールナイトニッポンが好きで、いっつもラジオの話ばかり聞かせてくれた。
その影響で私もラジカセを買った。
北杜夫を私に教えてくれたのは、
合唱クラブの先輩・建石徹さん。
とにかく、「船乗りクプクプの冒険」は面白いから読んでみて。
と、私にではなく、他のだれかに言っていたのを聞きかじり
私も買って読んでみたら メチャクチャ面白くて
それ以降、北杜夫にはまり、ドクトルマンボウシリーズも、さみしい王様も読破した。

この本は、逆に私が吉澤くんに「面白いから読んでみな。」と薦め、
やはり彼がおおいにうけ、はまっていった。
そして、私の以降の人生に大きく関わった
「石森章太郎・サイボーグ009」を教えてくれたのが
上島貞憲くんだった。

彼は文庫本全巻を持っており、数巻づつ貸してくれ、
読み終わるとまた次の巻を渡してくれるという。
全10巻。読み終えるのに時間はかからなかった。
これ以降、私は少年漫画にもはまっていったのだった。
と、中学時代、私の人格を形成するのに大いなる影響を与えたであろう
いろいろな事柄を教えてくれたのは全て同級生
それも男子達だった。
他にもハム(アマチュア無線)の試験を受けに一緒に勉強したり、
男子達は私の知らない世界の扉を開けてくれた。
女子から何も影響がなかったというわけではないが、
あまり琴線に触れるような刺激的なことはなかったように記憶している。
というか、あまり記憶がない・・・・・・。
なので女子高校に進んだ私に刺激を与えてくれる男子達が
周りからいなくなったことは、
私にとって非常に世間の様々なことを知る機会が喪失した
と言っても過言ではないような気がする。
中学時代、君達に教えてもらったんだよ。
たとえ誹られようとも
先日の「伊那小学校レイアウト図」について
ある同級生から
『下手』
という衝撃的な言葉をかけられてしまった。
下手という言葉 かなり強い言葉と思う。
ちょっと傷付いた。
(いや、かなり傷付いた)
下手の根拠としては、
・縮尺が違いすぎる。
全体としてのイメージが異なってしまう。
自分の言い訳としては、縮尺は無視して描いている。
記憶というものは曖昧で、
強烈に残っているものは大きく出るし、
忘れそうなものは小さくなってゆく。
ものだと思っている。
だから今回の平面図は
どこに何があったかがわかるように
という意図の下、描いたのだが
こだわる人にとっては、縮尺の違いが気になるようだ。
航空写真があったはずだから、図書館に行って
調べてみたら とのアドバイスもいただいたが
そこまでして描くつもりもない。
このレイアウト図も、どこに何があったか
間違っている。
あったものが描かれていなかったりする。
(鉄筋校舎と南体育館廊下の間に小屋があったはず)
時々、想い出しては描き足したり、修正したりしている。
今は正門から北側を描いている。
でも、なんだか描こうというモチベーションが
この件でガッと下がってきてしまった・・・・・・。
何か発信すれば何らかの反応が返ってくるのは
仕方ないことだけれど、
こういう反応はちょいと哀しい。
同窓生との話のネタになるかな、という想いから
描き始めたこの図。
なんだかおかしな方向へ行き始めちゃったゾ・・・・・・。
だからお願いがあります。
ここにこんなものがあったはず とか、
これはこっちにあったよ
という指摘はウェルカムです!
私の記憶を補完してくださる意見ならもちろん歓迎します。
そして、縮尺が気になるのであれば
どう描けばいいか教えて下さい。(具体的に)
ひとつだけ。
指摘のひとつに「うさぎ小屋」の位置は
2年生の校舎の西側、緑ヶ丘幼稚園の隣の
伊那小田んぼの下では?
とおっしゃっているが、そこにあったのは焼却炉です。
その下には2年生のトイレがあった。
うさぎ小屋は確かに貯水池の隣に
小学校3年か4年の時にできたはず。
皆でその小屋を作った記憶がある。
その隣には「ちゃぼ小屋」があったし。
(これだけは記憶にあるので譲れない)
私って打たれ弱いのよ・・・・・・・。
凹みます。
たとえ誹られようとも
なんて、カッコイイこと言えません。
そんなこと言われたらぴ~~~っと泣いて帰ります。
伊那小学校レイアウト図①
やっぱり舌の根も乾かぬうちからやっぱり更新しちゃってる・・・・・
だってね、このあいだの幹事慰労会の最後のほうで
しみずや・牧田君たちと盛り上がった話。
「伊那小学校のレイアウトはどうだった?」
特に牧田君は【粘土窯」がどこにあったか知りたがっていた。
ので、私はざっと図に描いたが それだとあまりに大雑把すぎたので
ちゃんと描き起こそうとチャレンジしてみた。
しかし、自分の記憶もいまいち曖昧な箇所があり、
どうしても2年生昇降口から校士さんのうち、石炭室のあたりがあやふやだ。
あ、今思い出した。
校士さんのうちと石炭室は逆だ。
石炭室はもっと北体育館の用具室の近くだった!
直しておかなくちゃ。
そして、南体育館を回る廊下も曖昧・・・・・・。
Web.用に縮小しちゃっているから、ちゃんと見えるかな?
これをもっと広げて全体図も描こうっと。
このあとは、大玄関から5年生の校舎まで。
レイアウト図(平面図)が描けたら次は立面図だ。
小学校が描けたら次は伊那中だ!
(まだまだこのブログ、想い出ネタで続くような気がする・・・・・・)
ご興味のある人はもうしばらくおつきあいのほどを!

だってね、このあいだの幹事慰労会の最後のほうで
しみずや・牧田君たちと盛り上がった話。
「伊那小学校のレイアウトはどうだった?」
特に牧田君は【粘土窯」がどこにあったか知りたがっていた。
ので、私はざっと図に描いたが それだとあまりに大雑把すぎたので
ちゃんと描き起こそうとチャレンジしてみた。
しかし、自分の記憶もいまいち曖昧な箇所があり、
どうしても2年生昇降口から校士さんのうち、石炭室のあたりがあやふやだ。
あ、今思い出した。
校士さんのうちと石炭室は逆だ。
石炭室はもっと北体育館の用具室の近くだった!
直しておかなくちゃ。
そして、南体育館を回る廊下も曖昧・・・・・・。
Web.用に縮小しちゃっているから、ちゃんと見えるかな?
これをもっと広げて全体図も描こうっと。
このあとは、大玄関から5年生の校舎まで。
レイアウト図(平面図)が描けたら次は立面図だ。
小学校が描けたら次は伊那中だ!
(まだまだこのブログ、想い出ネタで続くような気がする・・・・・・)
ご興味のある人はもうしばらくおつきあいのほどを!

高校同窓会スライドショー
中学の同窓会の6月のちょうど1か月前
5月23日に高校の同窓会が開催される。
これの幹事をやっている。
製作物を担当しようと、懇親会用のパンフレットと
学年会用のスライドショー、招待状を作成している。
スライドショーは当時の写真を他の幹事さんから集め、
Windows ムービーメーカーで作っている。
クラスがAからGまでの7クラス。
その写真が集まったのだが、ほとんどが修学旅行の集合写真。
どう編集するか悩んだ。
でも、中には弥生祭の演芸大会のものもあり、なんとかストーリーをつくり
完成させることができた。
全体を通して何回か自分でも見てみたのだが、なんだか涙が
出そうになる。
ちょっと感動させたい、という下心があったんだけど、
まんまと自分がはまっている・・・・・・・。
学年会というのは、同窓会総会・懇親会の後に
自分達の学年だけが集まっての会。
実はこの学年は弥生の最後の女だらけの学校の学年だった。
私達が卒業した4月に男子生徒が入学してきたのだ。
だから、3,2年は女子だらけだけど、1年生は男女混合という学校になったのだ。
私は学年会にも文化祭のようなスローガンが必要だと思い、
「最後の乙女花 それが私達!」
と付けた。
なので、スライドショーもそのスローガンにのっとって
女だらけ・・・・・・ というのを主題としたストーリーにしてみた。
でも、わざわざそんなスローガンが無くても写真を見たら
女だらけというのは一目瞭然だ。
弥生ヶ丘高校同窓会まであと2週間ちょっと。
最後の幹事会が13日にある。
そこで、学年会会場でスライドショーの動作確認をする。
ちゃんと写るかの確認だ。
最後まできっちりと仕事をする。
幹事の仕事も大変。

あんまりこの場ではネタばらしができない。
(中学の同窓生で弥生の同窓生もいるので、これ見ていると思うので・・・・)
この写真。
写っているのは伊那北高校の落語研究会の面々だ。
私は高校1年の時、10か月ほど落研に入っていた。
これは弥生祭の際、伊那北落研と交流会をした時のスナップ。
だから私、「寿限無」の名前を全部言える。
(いや、名前だけ。噺はできません)
前回の中学同窓会では、スライドショーを作って会場で流し、
後にDVDに焼いて希望者に配った。
今回の同窓会では、スライドショーはやらない。
だけど、高校のスライドショーを作ってみると
やっぱり中学のも欲しいなあ・・・・と思ってきてしまった。
前回のでもいいので、また流そうか。
人呼んで「しゃべくり仮面」
小学校1,2年生の頃 私は修組だった。
そのクラスに「H野」さんという友達がいた。
先日、高校の同窓会幹事会で彼女と会った。
機会があり、話したのだが彼女は私のことはすっかり忘れており、
想い出してもらえなかった。
彼女H野さんは、お父さんが国鉄バスに勤められていて、
天竜町にあった国鉄官舎に住んでらした。
よくそこへ遊びに出掛けた。
H野さんは、いわゆる今で言う「わらかし」が好きで、
おちゃらけで、おしゃべりで、明るくて、おちゃめな子だった。
だけれど、いつもお母さんに「落ち着きが無い」と叱られていた。
今でも覚えているのは、その頃テレビアニメで放映されていた
「遊星仮面」という番組で
「だれだ!」と叫ぶと
「ひとよんで 遊星仮面」
というフレーズが 流行っていた。

H野さんは、「ひとよんで 遊星仮面」というフレーズを
「ひとよんで しゃべくり仮面」
と変えて、背にはマントを羽織り、(ふろしきだった)
めがねをかけて
そんな様相で表れ、遊んだ。
それを彼女に話したかったのだが、私自身のことすら忘れているくらいだから、
そんなことは欠片も覚えていないだろう、と話すのをやめた。
H野さんはその後、転校していった。
高校で違う中学から入学してきた時は、また再会した、と思ったが
高校時代はクラスも違ったので、特段話しもしなかった。
あれから42年ほど経って、「しゃべくり仮面が・・・・」と言われても
何のことやらと思うのは当然だろう。
しかし、59歳の彼女を見ても
面白いものが好きで、明るくて、おちゃらけで、
という性格は変わってないように思う。
きっと、どの同級生に会っても、
あの頃とそうは変わってないように思う。
小学校や中学校の時の性格はそのまま大人になっても
変わってない。
人の本質はそう変わらないもの。
昔、中央病院があったバイパス沿いの対面に
国鉄官舎があったが、
今はもう壊され、全く違う風景が広がっている。
こうして景色は変わってしまったけれど、
人の記憶、人の本質は変わっていない・・・・・・・・・。
そのクラスに「H野」さんという友達がいた。
先日、高校の同窓会幹事会で彼女と会った。
機会があり、話したのだが彼女は私のことはすっかり忘れており、
想い出してもらえなかった。
彼女H野さんは、お父さんが国鉄バスに勤められていて、
天竜町にあった国鉄官舎に住んでらした。
よくそこへ遊びに出掛けた。
H野さんは、いわゆる今で言う「わらかし」が好きで、
おちゃらけで、おしゃべりで、明るくて、おちゃめな子だった。
だけれど、いつもお母さんに「落ち着きが無い」と叱られていた。
今でも覚えているのは、その頃テレビアニメで放映されていた
「遊星仮面」という番組で
「だれだ!」と叫ぶと
「ひとよんで 遊星仮面」
というフレーズが 流行っていた。

H野さんは、「ひとよんで 遊星仮面」というフレーズを
「ひとよんで しゃべくり仮面」
と変えて、背にはマントを羽織り、(ふろしきだった)
めがねをかけて
そんな様相で表れ、遊んだ。
それを彼女に話したかったのだが、私自身のことすら忘れているくらいだから、
そんなことは欠片も覚えていないだろう、と話すのをやめた。
H野さんはその後、転校していった。
高校で違う中学から入学してきた時は、また再会した、と思ったが
高校時代はクラスも違ったので、特段話しもしなかった。
あれから42年ほど経って、「しゃべくり仮面が・・・・」と言われても
何のことやらと思うのは当然だろう。
しかし、59歳の彼女を見ても
面白いものが好きで、明るくて、おちゃらけで、
という性格は変わってないように思う。
きっと、どの同級生に会っても、
あの頃とそうは変わってないように思う。
小学校や中学校の時の性格はそのまま大人になっても
変わってない。
人の本質はそう変わらないもの。
昔、中央病院があったバイパス沿いの対面に
国鉄官舎があったが、
今はもう壊され、全く違う風景が広がっている。
こうして景色は変わってしまったけれど、
人の記憶、人の本質は変わっていない・・・・・・・・・。
とびうおの歌
中学時代のクラブ活動。
私は、「合唱クラブ」。
担任の先生は音楽の先生で、吹奏楽クラブの顧問だった。
なので、入学したての頃、先生から
「吹奏楽クラブに入れば。パートはクラリネットかな。」と
誘われたことがあった。
反抗期の私は、素直じゃない私は
どーして先生の言いなりにならなくちゃいけないのよ・・・・
と、可愛くない発想で、合唱にした。
運動系のクラブも魅力的だったのだが、私の好きなバドミントン
は中学には無かったので、諦めた。
合唱クラブもなかなかハードな活動をしていた。
年間の一番大きな目標は『NHK合唱コンクール』への出場。
上伊那地区、南信地区、県大会とあり
最終的には全国大会を目指していたが
ほぼ上伊那地区予選で敗退していた。
NHKコンクールには、毎年課題曲とそれぞれの学校で選べる
自由曲というのがあり、
伊那中学校合唱クラブは毎年「とびうおの歌」を選曲していた。
顧問は女性の佐藤先生と言って、髪をポニーテールにした
怒るとちょっと怖い先生だった。
一年目の課題曲は「山の祭」
You tubeで探してみたらあった!
(便利な世の中ね~)
二年目の課題曲は「かたつむりのうた」
三年目 「遊園地の汽車」
覚えている歌もあり、忘れていたけれどこれを聴いて思い出したものもあり
でも全てが懐かしい。
ありましたよ!まさかの「とびうおの歌」も!
私が一年生の時、文化祭での合唱クラブの出し物は
単なる合唱ではなく、オペラをやった。
「かぐや姫」だった。
3年生が主に役付きで。私たち下級生は後ろでコーラス隊をしていた。
でも、ちゃんと衣装を付け、台詞もあり、楽しかった。
先輩の有賀さんがかぐや姫役で、
うちき食堂の息子さん内木先輩はおじいさん役だったかな?
1年生の時の先輩(3年生)というのは、ものすごい大人に感じて
例に漏れず私も3年生の先輩に憧れました。
(ピアノ教室の息子さんのT先輩・・・・)
合唱コンクールは夏休み明けだったので、夏休み中も練習があり
登校をしていた。
隣の音楽室では、同じように吹奏楽部も練習をしていた。
皆、夏の終わりにコンクールがあったり、試合があったりで
夏休み返上で練習に学校へ来ていた。
今回の同窓会。
クラスごとにテーブル席を設けるのだが、
こうしたクラブ活動の仲間と集まる というのも
やってみたいと幹事から声が上がっている。
バレーボール部、バスケ部、吹奏楽部、サッカー部、野球部、柔道部、剣道部・・・・・・
いろんな部活動ごとに集まるのも楽しい。
合唱や吹奏楽やギタマンは同窓会で演奏、合唱できたらと思うけれど
即興じゃできないし・・・・・
皆、もう楽器も持っていないかもだし。
せめて合唱クラブメンバーで集まって、「とびうおの歌」歌えないかな・・・・・・?
私は、「合唱クラブ」。
担任の先生は音楽の先生で、吹奏楽クラブの顧問だった。
なので、入学したての頃、先生から
「吹奏楽クラブに入れば。パートはクラリネットかな。」と
誘われたことがあった。
反抗期の私は、素直じゃない私は
どーして先生の言いなりにならなくちゃいけないのよ・・・・
と、可愛くない発想で、合唱にした。
運動系のクラブも魅力的だったのだが、私の好きなバドミントン
は中学には無かったので、諦めた。
合唱クラブもなかなかハードな活動をしていた。
年間の一番大きな目標は『NHK合唱コンクール』への出場。
上伊那地区、南信地区、県大会とあり
最終的には全国大会を目指していたが
ほぼ上伊那地区予選で敗退していた。
NHKコンクールには、毎年課題曲とそれぞれの学校で選べる
自由曲というのがあり、
伊那中学校合唱クラブは毎年「とびうおの歌」を選曲していた。
顧問は女性の佐藤先生と言って、髪をポニーテールにした
怒るとちょっと怖い先生だった。
一年目の課題曲は「山の祭」
You tubeで探してみたらあった!
(便利な世の中ね~)
二年目の課題曲は「かたつむりのうた」
三年目 「遊園地の汽車」
覚えている歌もあり、忘れていたけれどこれを聴いて思い出したものもあり
でも全てが懐かしい。
ありましたよ!まさかの「とびうおの歌」も!
私が一年生の時、文化祭での合唱クラブの出し物は
単なる合唱ではなく、オペラをやった。
「かぐや姫」だった。
3年生が主に役付きで。私たち下級生は後ろでコーラス隊をしていた。
でも、ちゃんと衣装を付け、台詞もあり、楽しかった。
先輩の有賀さんがかぐや姫役で、
うちき食堂の息子さん内木先輩はおじいさん役だったかな?
1年生の時の先輩(3年生)というのは、ものすごい大人に感じて
例に漏れず私も3年生の先輩に憧れました。
(ピアノ教室の息子さんのT先輩・・・・)
合唱コンクールは夏休み明けだったので、夏休み中も練習があり
登校をしていた。
隣の音楽室では、同じように吹奏楽部も練習をしていた。
皆、夏の終わりにコンクールがあったり、試合があったりで
夏休み返上で練習に学校へ来ていた。
今回の同窓会。
クラスごとにテーブル席を設けるのだが、
こうしたクラブ活動の仲間と集まる というのも
やってみたいと幹事から声が上がっている。
バレーボール部、バスケ部、吹奏楽部、サッカー部、野球部、柔道部、剣道部・・・・・・
いろんな部活動ごとに集まるのも楽しい。
合唱や吹奏楽やギタマンは同窓会で演奏、合唱できたらと思うけれど
即興じゃできないし・・・・・
皆、もう楽器も持っていないかもだし。
せめて合唱クラブメンバーで集まって、「とびうおの歌」歌えないかな・・・・・・?
小学校時代の話
中学校の同窓会ブログなんだけれど、時々小学校の話も紛れる。
伊那中学校は、伊那小学校と伊那西小学校の生徒が通った。
伊那小学校は『友がき2000おこたらず』と校歌にあるように、
2000人も生徒数がいたマンモス小学校だったから、
伊那中学校もその人たちの持ち上がりで、伊那小卒業生が大半を占めていた。
だから、伊那小の話も同窓会メンバーでよく語られる。
(その点はいつも西小卒業生の皆さんには申し訳ないと思ってます)
昨日、私の地域の皆さんとの飲み会での会話で、
学校時代の話になった。
私以外の皆さんは私より年上。
でも、だいたい同じような想い出。
まずは冬のだるまストーブの話。
石炭入れというバケツがあり、石炭場に行き、スコップでバケツに石炭を入れ、
教室まで運んだのだが、年代により石炭fではなくコークスだった という話もあり、
(コークスの方が新しい?)
私たちの頃は石炭だったなあ・・・・・・・・。
火を点ける時は、「たきつけ当番」というのがあり、
近所の林から薪を拾い、中に新聞や広告やおが屑を詰め、
持って行き、火を点けた。
煙突にススが貯まり、先生が火掻き棒で煙突を叩き、
詰まったススを落とすんだけれど、それでも詰まり、
教室中が煙だらけになって、授業は中止なんてことも。
下に正方形の敷台があり、ストーブの上には蒸発桶に水が入れられ、
ストーブの近くには水がいっぱい入ったバケツが置かれていた。
ストーブの近くの人は、顔が焼けるようになり、
一番遠い窓際の人たちは、窓の隙間から雪が降ってきて
凍えるような寒さの中、授業を受けていた。
(木枠のガラス窓だったからね)
それと、学校には「校用技士」さん 「校士」さんと呼ばれる人がおり、
大きな釜でぐらぐらとお湯を沸かしてくれて、
掃除の時間になるとバケツを持って、そこへ行き
お湯をバケツの赤い線のところまで入れてもらい
水を足して雑巾掛けをした。
冬場は掃除時間の後のほうになると、お湯が冷め、ほとんど水。
雑巾掛けをすると、凍って、滑って先へ進めなかった。
学校のトイレ。
水洗トイレにお目にかかれたのは私が大学に行ってから。
小中高と全部 ぽっとんトイレだった・・・・・・・・・。
小学校は古い木造校舎。
トイレももちろん古~~~~い。
普通、トイレの便器というのは白い。
が、小学校のトイレは違った。
まるで骨董屋で扱っているような陶器製の模様の入ったものだった。

なんだか、お城の殿になった気分?
いや、このトイレ、本当に怖かった。
暗いし、ぽっとんの穴が筒状ではなく、1列全部貫いて開いていたのだ。
落ちたらどうなる?と想像しただけで恐ろしくなった・・・・・
(いや、想像したくない・・・・・!!)
このトイレももちろん素手で雑巾掛けをした。
ブラシなんてものも使わず、素手で拭いた。
それはそれは、トイレの神様に相当褒められたことだろう。
小学校の話、校舎の話、まだまだモリモリだくさんにある。
それは追々また話してゆこうと思う。

この画像は伊那小学校の鉄筋校舎。3,4年生が入っていた。
(この画像はこのブログからお借りしました。)
「東日本 近代建築万華鏡」
伊那中学校は、伊那小学校と伊那西小学校の生徒が通った。
伊那小学校は『友がき2000おこたらず』と校歌にあるように、
2000人も生徒数がいたマンモス小学校だったから、
伊那中学校もその人たちの持ち上がりで、伊那小卒業生が大半を占めていた。
だから、伊那小の話も同窓会メンバーでよく語られる。
(その点はいつも西小卒業生の皆さんには申し訳ないと思ってます)
昨日、私の地域の皆さんとの飲み会での会話で、
学校時代の話になった。
私以外の皆さんは私より年上。
でも、だいたい同じような想い出。
まずは冬のだるまストーブの話。
石炭入れというバケツがあり、石炭場に行き、スコップでバケツに石炭を入れ、
教室まで運んだのだが、年代により石炭fではなくコークスだった という話もあり、
(コークスの方が新しい?)
私たちの頃は石炭だったなあ・・・・・・・・。
火を点ける時は、「たきつけ当番」というのがあり、
近所の林から薪を拾い、中に新聞や広告やおが屑を詰め、
持って行き、火を点けた。
煙突にススが貯まり、先生が火掻き棒で煙突を叩き、
詰まったススを落とすんだけれど、それでも詰まり、
教室中が煙だらけになって、授業は中止なんてことも。
下に正方形の敷台があり、ストーブの上には蒸発桶に水が入れられ、
ストーブの近くには水がいっぱい入ったバケツが置かれていた。
ストーブの近くの人は、顔が焼けるようになり、
一番遠い窓際の人たちは、窓の隙間から雪が降ってきて
凍えるような寒さの中、授業を受けていた。
(木枠のガラス窓だったからね)
それと、学校には「校用技士」さん 「校士」さんと呼ばれる人がおり、
大きな釜でぐらぐらとお湯を沸かしてくれて、
掃除の時間になるとバケツを持って、そこへ行き
お湯をバケツの赤い線のところまで入れてもらい
水を足して雑巾掛けをした。
冬場は掃除時間の後のほうになると、お湯が冷め、ほとんど水。
雑巾掛けをすると、凍って、滑って先へ進めなかった。
学校のトイレ。
水洗トイレにお目にかかれたのは私が大学に行ってから。
小中高と全部 ぽっとんトイレだった・・・・・・・・・。
小学校は古い木造校舎。
トイレももちろん古~~~~い。
普通、トイレの便器というのは白い。
が、小学校のトイレは違った。
まるで骨董屋で扱っているような陶器製の模様の入ったものだった。

なんだか、お城の殿になった気分?
いや、このトイレ、本当に怖かった。
暗いし、ぽっとんの穴が筒状ではなく、1列全部貫いて開いていたのだ。
落ちたらどうなる?と想像しただけで恐ろしくなった・・・・・
(いや、想像したくない・・・・・!!)
このトイレももちろん素手で雑巾掛けをした。
ブラシなんてものも使わず、素手で拭いた。
それはそれは、トイレの神様に相当褒められたことだろう。
小学校の話、校舎の話、まだまだモリモリだくさんにある。
それは追々また話してゆこうと思う。

この画像は伊那小学校の鉄筋校舎。3,4年生が入っていた。
(この画像はこのブログからお借りしました。)
「東日本 近代建築万華鏡」
中学時代は反抗期?
あの頃の教師というものは、絶対的な存在であった。
いまどきならパワハラで訴えられても仕方ないようなこともしていた。
中学時代というと、ちょうど反抗期の時代。
私ももれなく反抗期であったと思う。
私の担任はかの有名なK先生。
あだ名は「ひこーきでっぱ」。
その由来は、挨拶するときに飛行機のように手が翼のように下15度の角度で
開き、後はお顔の印象から・・・・・。(失礼)
この先生、今思い返すに とにかく封建的。
ご自分の主義主張が正義であり、生徒達はそれに絶対服従であった。
そして、それに逆らったり、違反をすると必ず『罰』が下された。
生徒によってはその罰をくらいやすい人と、避けれた人がいた。
その違いは、まじめか不真面目かの違いなんだけれどね。
宿題をし忘れてくる。
忘れ物をしてくる。(教科書とか、リコーダーとか絵の具とか、体操着とか)
朝掃除に遅れる。
授業中に騒がしかった。
まあ、こんな理由でK先生から罰をくらう。
罰の内容は 『グランド10周』!
『うさぎとび体育館5週』なんてのもあった。(雨の日のグランドの替り)(死ぬゾ)
『教室全部の床掃除往復5往復』なんてのも。
教室の後ろにも黒板があり、そこにその罰が書き出される。
グランド10周が積み重なり、グランド500周くらいになっていた。
そんな奴もいた。
私? 私は、間違いなく不真面目な側。
女子はあまり罰をもらう人は少なかったのだが、
もう一人の女子・Hさんと一緒に私はクラスでもトップクラスであった。
こんな逸話が。
中学一年生の時に、長距離マラソン1kmくらいだったかな、
クラスの皆で走ったのだが、私の順位は最下位。本当にビリっけつ。
そしてグランド10周を走り続け、床掃除をし続け、うさぎとびをし続けた私は
中学3年時にはなんと、女子1位、男子も抜かす長距離選手になっていた・・・・。
(自慢にならん!)
私は、この『罰』というやり方がメチャクチャ嫌いだった。
K先生に対して、生活記録帳に反論を書いた。
そのたびにその反論がK先生の逆鱗に触れ
よけいにグランド10周が増えていった。
罰が嫌いなら、まじめに朝早く起きて朝掃除に遅れなければいいだけの話
なのだが、そこらへんが中学生の浅はかさで、
屁理屈だけはイッチョ前で、行動が全く伴ってないの典型。
とにかく、忘れ物をする→罰をくらう→反抗する→罰が増える
この繰り返しだった。
今だったら、あの頃の私に言ってやりたい。
「もう少しうまく生きなさい。」と。

いまどきならパワハラで訴えられても仕方ないようなこともしていた。
中学時代というと、ちょうど反抗期の時代。
私ももれなく反抗期であったと思う。
私の担任はかの有名なK先生。
あだ名は「ひこーきでっぱ」。
その由来は、挨拶するときに飛行機のように手が翼のように下15度の角度で
開き、後はお顔の印象から・・・・・。(失礼)
この先生、今思い返すに とにかく封建的。
ご自分の主義主張が正義であり、生徒達はそれに絶対服従であった。
そして、それに逆らったり、違反をすると必ず『罰』が下された。
生徒によってはその罰をくらいやすい人と、避けれた人がいた。
その違いは、まじめか不真面目かの違いなんだけれどね。
宿題をし忘れてくる。
忘れ物をしてくる。(教科書とか、リコーダーとか絵の具とか、体操着とか)
朝掃除に遅れる。
授業中に騒がしかった。
まあ、こんな理由でK先生から罰をくらう。
罰の内容は 『グランド10周』!
『うさぎとび体育館5週』なんてのもあった。(雨の日のグランドの替り)(死ぬゾ)
『教室全部の床掃除往復5往復』なんてのも。
教室の後ろにも黒板があり、そこにその罰が書き出される。
グランド10周が積み重なり、グランド500周くらいになっていた。
そんな奴もいた。
私? 私は、間違いなく不真面目な側。
女子はあまり罰をもらう人は少なかったのだが、
もう一人の女子・Hさんと一緒に私はクラスでもトップクラスであった。
こんな逸話が。
中学一年生の時に、長距離マラソン1kmくらいだったかな、
クラスの皆で走ったのだが、私の順位は最下位。本当にビリっけつ。
そしてグランド10周を走り続け、床掃除をし続け、うさぎとびをし続けた私は
中学3年時にはなんと、女子1位、男子も抜かす長距離選手になっていた・・・・。
(自慢にならん!)
私は、この『罰』というやり方がメチャクチャ嫌いだった。
K先生に対して、生活記録帳に反論を書いた。
そのたびにその反論がK先生の逆鱗に触れ
よけいにグランド10周が増えていった。
罰が嫌いなら、まじめに朝早く起きて朝掃除に遅れなければいいだけの話
なのだが、そこらへんが中学生の浅はかさで、
屁理屈だけはイッチョ前で、行動が全く伴ってないの典型。
とにかく、忘れ物をする→罰をくらう→反抗する→罰が増える
この繰り返しだった。
今だったら、あの頃の私に言ってやりたい。
「もう少しうまく生きなさい。」と。